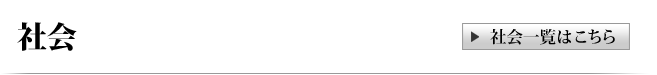
小・中学校の義務教育期間中に行なわれる学校行事のひとつに「修学旅行」がある。年齢を重ねても良き思い出のひとコマとして残っているものだが、時代の移り変わりとともに記憶される風景は変わっているようだ。
近年はテーマパークやスキー場が旅行先のメインになっているというので、福岡市の中学校に関する修学旅行事情を調べてみた。
結論から言って、疑問が残る実態である。
USJとスキー場で7割
 HUNTERが福岡市教育委員会に情報公開請求して入手したのは、福岡市立の中学校70校の平成20年度から22年度までの3年間における修学旅行の日程(うち1校は修学旅行を実施していない)。
HUNTERが福岡市教育委員会に情報公開請求して入手したのは、福岡市立の中学校70校の平成20年度から22年度までの3年間における修学旅行の日程(うち1校は修学旅行を実施していない)。
旅行先は、定番ともいえる関西方面が中心となっているが、とくに目立つのが「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」(以下、USJ)だった。
平成20年が36校、21年が35校、22年には37校がUSJを旅行先のひとつに選んでおり、毎年5割以上の中学が似たような日程を組んでいる。
初日にUSJを訪れ、2日目で京都市内自主研修、3日目は奈良公園というコースだ。
3日間とも「スキー場」という修学旅行もある。こちらは主として山陰・中国地方だが、平成20年度16校、21年度12校、22年度10校がスキー場で2拍3日の日程を消化していた。
右の一覧表は平成22年度の各校の旅行日程だが、全体で7割近くの中学がUSJかスキー場を選んでいたことになる。
毎年、沖縄、東京など他校とはまったく違う旅行先を選んでいる学校もあるが、全体のなかでは1~2校程度でしかない。
素朴な疑問
福岡市だけでなく、他の自治体にある多くの中学校も同様の傾向にあるのだというが、疑問に感じるのは、USJのようなテーマパークやスキー場を訪れることが修学旅行の趣旨に沿ったものなのかという点。「修学」とは「学を修める」ということのはずだが、テーマパークやスキー場が、果たしてそこにつながるのだろうか。
USJやスキーが「修学」と言えるのか。福岡市教育委員会の学校指導課に話を聞いた。
担当職員の説明によれば、修学旅行は文部科学省が中学校学習指導要領のなかで定めた「旅行・集団宿泊的行事」にあたるとしたうえで、USJについては、国際理解を深める教育や異文化理解の一環として見ているのだという。
たしかに、中学校学習指導要領・第4章「特別活動」には『学校行事』について次のように記されている。《学校行事においては、全校又は学年を単位として、学校生活に秩序と変化を与え、集団への所属感を深め、学校生活の充実と発展に資する体験的な活動を行うこと》。
さらに『旅行・集団宿泊的行事』として《平素と異なる生活環境にあって、見聞を広め、自然や文化などに親しむとともに、集団生活の在り方や公衆道徳などについての望ましい体験を積むことができるような活動を行うこと》とある。
そもそも学習指導要領に記された「旅行・集団宿泊的行事」についての定義自体が「修学」一辺倒ではなく、受け取り方次第で幅広く解されるもののようだ。
要領に照らせば、テーマパークやスキー場への旅行が目的を外れているとは言えないのだが、やはり"学を修める"というよりレジャーに近いとしか思えない。
なにより、毎年度の修学旅行の日程を見ていると、どうしても違和感をぬぐえない。
これは、前述したように各学校の旅行日程がUSJ→京都→奈良公園のように、ほぼ同じとなっていることからくるものだ。
同一日程への疑問
市教育委員会に、修学旅行の行く先選定の過程を確認したところ、学校ごとの自由裁量で決めており、旅行の行く先について教育委員会が指定することはないという。
同教委が定めているのは、引率教員数(学級数×1.5+2名)や旅行費用の上限(50,000円)、実施学年(2年時)のほか、旅行業者選定にあたって3社以上の見積もりをとることなどだという。
ならば、どうしてどの中学校もほぼ同じ日程になるのだろう。
念のため、各校が旅行業者から提出を受けた見積書や旅行先選定理由がわかる文書の開示を求めたが、教育委員会は該当文書を保有しておらず、各校から取り寄せることになるため時間がかかるという。
つまり市教委としては、業者選定時のチェックを行なっていないということになる。
市教委による情報開示を待って、改めてその問題点を検証する予定だ。
